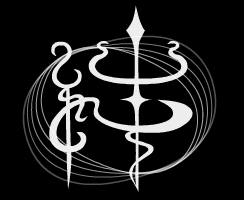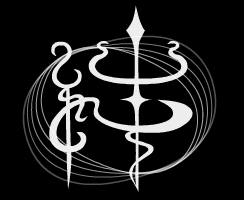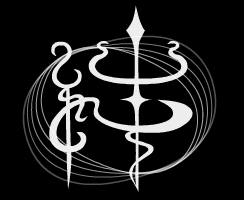
絆
蝋燭の弱い光が冷たい壁に跳ね返り、小さな部屋を満たしていた。
それをさえぎり落とした影の先に、ジュナが小さく横たわる。
ジュナの体温を伝えるように、二人の間の空気はわずかに熱を帯びていた。
髪を撫でると、小さな息づかいが聞こえてくる。
「本当に…私でいいの?」
締め付けられたような細い声でジュナが言う。
「…うん」
普段とは違うジュナの弱々しさに戸惑いながらも、
力を込め、はっきりと答える。
「好きだよ、ジュナ」
「…!」
今度は言葉にならない声が、かすれた呼吸となってジュナの口から漏れた。
今ここまで縮めてきた距離、その最後の一歩を惜しむように、
ゆっくりと体を寄り添えてゆく。
顔を近づけて、目の前いっぱいになったジュナの瞳を覗くと、
こぼれ落ちそうに揺らめいて、やわらかい光をたたえていた。
ジュナの頬にふわりと手を当てる。
上気した顔で瞳を細めていたジュナは、
困惑するように、その視線を下げた。
触れ返してくるジュナの手も、柔らかい感触の奥で少しこわばり、
どこかぎこちなく、首筋を撫でながらさまよった。
左手をかざし、ジュナの額を覆う。
「ジュナ、 …怖い?」
「ううん…違うの」
そう言いながらも、ジュナは顔をうつむいて
きゅっと目をつむる。
背中にまわったジュナの腕に、力がこもった。
「こんなこと、…こんな気持ちも、初めてだから…
凄く嬉しいのに、こんなに好きなのに、
どうしたらいいのか、分からなくて…」
ジュナの表情は、その言葉以上に、不安の色を帯びていた。
少しずつ縮まっていくかのように見えた距離は、
最後の最後にそれを拒もうとする。
長い年月をまたぐように、二人の沈黙は続いた。
--------------------------------------------------------------
王は激しく苛立っていた。
王子は、ついに反逆分子としてその本性を現した。
王の知らぬ間に、王子は「敵国」の偵察に赴いていのだ。
王子が秘密裏にそれを行ったという事…
疑いの目は間違いなく王に対して向けられており、
王はそれにもっと早く気づくべきだった。
王子は、王を差し置いて国民の強い信頼を得ていた。
王子が事実を知り国に帰れば、すぐにもそれは国中に知れわたるだろう。
やむなく王は、王子を始末すべく兵を差し向けた。
しかし、よりにもよって、奴らは王子を仕留め損ねたのだ。
それは王子の抱く「疑い」を、「確信」へと変える行為に他ならなかった。
兵の姿を見れば、それが「敵国」の者でないことは、明白だからだ。
--------------------------------------------------------------
王子は恐るべき事実に直面していた。
王子が抱いていた疑いは、やはり誤りではなかった。
王子も国民も、王によって欺かれていたのだ。
護衛の者たちは、王子を守って倒れた。
そして王子もまた、深い傷を負っていた。
王子は何としても国に帰り、全てを国民に伝えなかればならなかった。
強い日差しが照りつけていた。
青々とした草原は、その匂いを辺り一面に広げる。
ふっと体の力が抜け、王子の頬に柔らかいものが触れた。
草原に倒れこんだかと思ったが、そうではなかった。
優しい瞳が、王子の顔を覗き込んでいた。
王子はそれをかすかに感じ、そして意識が遠のいていった。
--------------------------------------------------------------
目を覚ました王子の目に、王子を懸命に介抱する彼女の姿が映った。
その姿は王子とは似つかぬものだったが、それを気にする様子もなく、
彼女は王子を深くいたわり、優しく手を差しのべた。
彼女は、この国の王女だった。
王子にとっても、姿の違いは何の意味も持たぬものだった。
王子は彼女に、言いつくせぬ感謝と、敬意を抱いていた。
しかし彼女に伝えるべき事実だけは、王子の心に重くのしかかった。
人間に対する大きな失望と軽蔑、それが王子自身にも及ぶことを覚悟し、
王子は全てを話した。
王女は驚き、悲しんだ。
しかし、王子に対する優しさを変えることはなかった。
王子の傷は、少しずつ癒えていった。
二人の間に愛が芽生えるのに、時間はかからなかった。
それぞれに背負っている大きなものの狭間で、そして限られた時間の中で、
二人はその愛を、熱く育んでいった。
それが永遠であればいいと、互いが思っていることを知り、
しかしどちらも、口に出すことはなかった。
草原には小さな花が色とりどりに咲き乱れ、
日ごとにその姿を変えていった。
王女は、彼女に宿った命のことを、王子に告げた。
王子は喜び、そして悲しんだ。
その日を待つ時間は、もう残されていなかった。
二人は新たな命を、ジュナと名づけた。
愛の証は、二人の愛をさらに深めた。
事態はそれほど深刻ではない、まだ急ぐことはないと、
溶けるように触れ合う体は告げていた。
それを引き剥がすのは、どちらにとっても身を裂く痛みだった。
王子は別れを告げ、必ず戻ってくると誓った。
王女と再び会うために、そしてまだ見ぬジュナに会うために。
--------------------------------------------------------------
ジュナは、生まれたままの姿で触れ合っていた。
それは今まで生きてきた中で、ジュナの身体と、そして心を守ってきた壁を
取り去ることであった。
そしてそれでもなお、ありのままのジュナが受け入れられている
ということでもあった。
恥ずかしくはなかった。
幾度も触れ合って、恥ずかしさを感じながら、ここまで来たのだから。
怖くもなかった。
熱くなったジュナの体は、もう求めることを止めなかった。
ジュナの中で渦巻いているのは、もっと大きくて、訳の分からない感情だった。
自分の心を求めてくれることと、自分の体を求めてくれること。
どちらも同じくらいに嬉しいのに、最後の最後でその両方を突き返してしまうことは、
ジュナ自身にも堪えられないことだった。
逃げ場を失った体温を開放するには、もう前に進むしかないのは分かっていた。
そして、今触れ合っているもう一つの体もまた、強くそれを求めていることも、分かっていた。
でも、今来られたら…代わりにその感情を、全て吐き出してしまいそうだった。
戸惑いの視線を感じながらもそれに応えることができず、
触れてくる柔らかい手にも、伝わってくる優しさにも
ジュナは体をこわばらせる事しかできなかった。
撫でられる度に、激しい感覚がジュナの体を走り、体は強くそれを求め、
本能以外の場所が、ジュナを苦しめた。
ジュナは触れてくる腕ごと、その体を強く抱きしめた。
こうして体をくっつけるよりも、本当はもっと近づきたいのに、
今は、背中以外を撫でられるのが怖かった。
抱き寄せた胸の中に顔をぎゅっとうずめる。
真夏のような蒸し暑さに、ジュナはむせかえりそうになった。
--------------------------------------------------------------
二人の体が少しずつ熱を高め、近づこうとするのを強く感じていた。
しかしジュナの表情は、変わらずそれを拒むかのようだった。
自分はジュナに拒まれているのか、自分の体がジュナに拒まれているのか、
それとも何か別の…
あれこれと考える余裕は、もう残っていなかった。
血は体中を熱く巡り、思考も、…理性も、遠くへ飛ばしてしまいそうだった。
胸の中で小さくなる、ジュナの弱々しさ。
普段とはあまりに違うその姿が、かろうじて理性をつなぎ止めていた。
ジュナの体を撫で上げると、柔らかい感触と共に、熱い吐息が伝わってくる。
でも今はそれすら、ジュナを苦しめてしまいそうだった。
ジュナの手が腕から背中に回り、強く抱きしめられた。
体中で触れ合う感触…今の自分には、もうそれだけでは足りなかった。
--------------------------------------------------------------
王子が「敵国」にかくまわれているとの報を受け、
失態がもたらした思わぬ結果に、
王は内心笑うのを隠すのに必死だった。
やがて王子はこの国に戻ってくるだろう。
王は準備を整え、それを迎えればよいだけだった。
王子は最後の砦として国民にすがりつくであろうが、
その時にはもはや、国民は王子の味方ではないだろう。
それが国民の、王への信頼を意味する訳ではないが、
国民が「敵国」の敵でありさえすれば、王には十分だった。
国民など、王にとっては単なる踏み台でしかなかった。
王子については、最初それを失うことに若干の迷いがあったものの、
今となっては躊躇する理由など何もなかった。
全ては、王のために。
--------------------------------------------------------------
知らせを受け、王女は嘆き悲しんだ。
隣国が兵を挙げたということ、それは、
これから始まろうとしている破滅的な戦い、
そして、最愛の人が辿ったであろう運命――
二つの絶望を、無惨にも王女に突きつけていた。
しかし今この場では、その一つを口にすることはできない。
眼前にある国、そして国民を導かなくてはならなかった。
王女は気強く振る舞い、取るべき道を模索した。
王女が選んだのは、和解への道だった。
だがそれもまた、多大な犠牲を払う、険しい道のりだった。
国、国民、王女自身、そして何よりこのジュナに対して、
大きな荷を背負わすことになる。
生まれながらにして、ジュナに課される使命――
ジュナは誰よりも強く、誰よりも優しくなり、
そして人間を受け入れ、人間に受け入れられなければならない。
長い長い闇と、孤独の中で。
もはや王女に出来るのは、ジュナを信じることと、神に祈ることだけだった。
ジュナが全てを乗り越えられるように。
そしてジュナの出会う「誰か」が、彼のような素晴らしい人間であるように。
--------------------------------------------------------------
気が付いた時には、ジュナは孤独だった。
唯一つ受けた深い愛情も、今では日ごとに遠くなり、
ジュナの記憶から薄れつつあった。
この暗く閉塞した世界と、自分の姿と、
そして時に現れ、ジュナを冷たく見据える者。
ジュナは苦しみの中で、自分が成すべきことを少しずつ理解し始めていた。
自分とは姿の異なる者たち――
始めそれが意味することが、ジュナには分からなかった。
ジュナの中に流れる血も、無垢な心も、何の迷いもなくジュナを人間へと近づけた。
しかしそれに対する答えは、ジュナの心を閉ざすのに充分だった。
ジュナは強くなった。しかしそれは、ジュナ自身を守るものでしかなかった。
身体も、心も、傷つくことのないように
人間との距離を保って生きるのが、ジュナには精一杯だった。
ある者は去り、ある者は倒れ、
何も分かり合うことのなかった無力感だけがジュナの心に積み重なり、
そしてまた非情な出会いは繰り返された。
人間がジュナを拒み、ジュナが人間を拒み…
世界が変化を恐れるかのように、長い間、それは循環を続けた。
やがてジュナの前に、一人の人間が現れるまで――
--------------------------------------------------------------
「ずっと… ずっと寂しかったの…!」
長い沈黙を破り、
突然、せき止めていた感情がなだれるように、
ジュナの言葉が、涙が、溢れ始めた。
「本当は何も違わないはずなのに、分かりあえるはずなのに、
誰も受け入れてくれなくて、避けられたりして、
繰り返してるうちに、段々それが怖くなって、
ずっと、一人ぼっちなんだって…
初めて会った時…もっとずっと前から、そう思ってて、
だから私、何もできなくって…」
唐突に吐き出されたジュナの言葉の多くは、
自分には理解し難いものだった。
嗚咽の中から搾り出すように、それは続く。
「それなのに、喋りかけてくれるし、触れ合ってくれるし、
それで、こんなに好きになってくれて、
こんなこと、今までなかったから…
私、どうしたらいいのか分からなくって…
…私だけ、こんなに幸せで、いいのかな、って…」
俺だって、幸せだよ。
とっさに口から出かけたその言葉を、慌てて飲み込む。
ジュナがそんな答えを求めていないのは、明らかだった。
ジュナの心に何が渦巻いているのか、
何を思い、こんなにも泣いているのか、
そして、この言葉が誰に向けられているものなのか…
それすらも分からなかった。
ジュナの奥にあるもの、ジュナが背負っているもの、
自分には想像もつかない何かが今、大きく横たわって、
二人の間を隔てているようだった。
ふいにまとわり付いたような、冷たい空気の存在。
それと共に、体が急速に冷めていくのを感じた。
後は、胸の中のジュナだけでも温めていてあげようと、
今はもうそれだけで充分だと、そう思った。
ジュナの泣き声が少しずつ小さくなり、
長く冷たい夜が、静かに更けようとしていた。
その時、胸元の空気がふわりと動いた。
ふいにジュナが、丸め込んでいた首筋をすっと伸ばし、
顔を近づけてきた。
涙に濡れた瞳は、息を飲むような美しさと、
…そして熱情を帯びていた。
静まっていた鼓動が、とくんと、大きく跳ねる。
少しの間見つめ合うと、ジュナはゆっくりと瞳を伏せ、
そして、口元を舐め始めた。
「ごめん…心配にして、ごめんね。
でも泣いたらね、なんか凄く安心して、
一緒にいてくれるのが凄く嬉しくて、
本当は私も、こんな風に、したかったのに…」
舌の出す音に混じって、ジュナの言葉が小さく聞こえてくる。
「だからね…やっと決められたの。
ちゃんと全部話すって。
話しても、きっと、大丈夫だって…」
残った涙が落ち、ジュナの頬に筋を描く。
「だから…絶対に、離れないでね…
絶対…、絶対だよ…」
その言葉の真意も理解できぬまま、不意の出来事に
半ばあっけにとられ、ジュナのするままに任せる。
こそばゆく、なまめかしい感触に、火はすぐにまた燃え上がった。
二人の間の壁が溶けたのは、体が理解していた。
ジュナの口を舐めかえすと、涙の味が舌に滲みわたった。
すぐに舌と舌が触れ、絡み合い、
次第にその動きを激しくしながら、二人の口の中を行き来する。
さっきまでジュナが顔をうずめていた場所――
二人の体のわずかな隙間に手を入れ、這わせる。
ジュナの体がぴくんと脈打ち、
吐息は渦を巻くように、口の間から漏れた。
ジュナの心の在り処を探すように、存在の全てを確かめるように、
ジュナの体をくまなく撫でてゆく。
さっきまでこわばっていたジュナの体は、
束縛から解放されたように、柔らかくそれを受け止めた。
全てを忘れ、何かに衝かれるように、熱い体が絡み合う。
するり、とジュナの舌が逃げた。
ジュナの感触に注いでいた全ての意識を引き戻し、
ゆっくりと目を開ける。
少しの距離をおいて、ジュナの瞳が再びこちらを見つめていた。
火照った顔と荒い息をなだめながら、ジュナは優しく微笑む。
「 …お願い。」
この見知らぬ世界と、これからジュナが語ろうとしている何か。
巨大な壁を前にしながら、それでも、ジュナと固くつながることができた。
いつかジュナと本当の絆を結び、ジュナの全てを救おうと、心に誓った。
もうジュナが、泣くことのないように。
(終)